
先日、総務省行政評価局が行っていた「生活道路における交通安全対策に関する政策評価」の結果が公表されていました。以前、この政策評価の「中間報告」について書きましたが、最終的にどのような結果がでるのか楽しみにしていました。
この政策評価の報告書は、100ページ以上もあり、内容的が分かりにくい部分もあるので、少しずつ解読していこうと思います。
報告書と合わせて、その「要旨」が公表されていますので、まずは、これから見ていきます。
総務省がこの政策評価を行うことにした背景
主として地域住民の日常生活に利用される「生活道路」では、「幹線道路」に比べて交通事故の減少率が低くなっています。また、日本における交通事故の特徴として、歩いたり自転車に乗っている際に事故に遭って亡くなる方の割合が諸外国と比べて高くなっていたり、事故で亡くなる方の4分の1は、自宅から500m以内の身近な生活空間で発生した事故でのものになっています。
このような現状を受け、国が交通安全対策の方針を定めた交通安全基本計画(第11次)では、生活道路で行う交通安全対策として、「交通事故の多いエリアで対策をとること」、「ビッグデータを活用して潜在的高リスク箇所(事故は起きていないが将来事故が起きるリスクが高い箇所)の解消を進めること」が挙げられています。
総務省による政策評価の視点
生活道路での交通事故を道路別(国道・都道県道・市区町村道)にみると、事故の7割は市区町村道で発生しています。このため、総務省による政策評価は、市区町村による交通安全施設等の整備状況や、警察による市区町村の支援状況を対象に行われました。
市区町村ごとの交通安全施設等の整備の取組の違いが生活道路における交通事故件数の増減とどのように関係しているかを分析・評価して、市区町村がどのように取り組めば、事故減少に効果的であるかが検討されています。
評価の実施方法
評価の対象とした生活道路
法令上、生活道路の定義はなく、市区町村が考える生活道路の定義はバラバラのため、次に挙げた市区町村道での事故を生活道路における事故件数として集計しました。
①5.5m未満の単路、②5.5m以上9.0m未満の単路(中央分離なし)、③5.5m未満の道路同士の交差点、④5.5m未満の道路とそれ以上の車道幅員の道路との交差点、⑤5.5m以上13.0m未満の道路同士の交差点(信号機なし)
調査した市区町村
454市区町村を対象として、書面での基礎調査を行っています。令和元年に生活道路で発生した交通事故件数が多い市区町村(全国の交通事故件数の9割に達するまで抽出)を選定しています。
さらに、123市区町村を対象として実地での調査を行っています。基礎調査した市区町村の中から、地域バランスや特徴的な取組等を考慮して選定しています。
調査した市区町村の取組
市区町村が整備する交通安全施設のうち、区画線、カーブミラーなど比較的低予算・短期間で整備することができ、数多く整備されている施設に関する取組を中心に調査しています。
評価結果の要旨
市区町村は交通事故の発生状況を把握しているのか
- 交通事故の発生箇所を「おおむね把握している」と回答した市区町村は2割しかなく、「ほとんど把握していない」と回答した市区町村が2割もありました。
- 市区町村が交通事故の発生状況を把握する方法として、警察庁が公開している交通事故統計情報のオープンデータや、都道府県警察が公表している事故マップを使用する方法がありますが、市区町村からは「オープンデータの使い方が分からない。データを地図化するための余裕やスキルがない。」「都道府県警察事故マップの情報が不足している。」といった声が聞かれました。
市区町村は交通安全施設を整備する箇所をどうやって決めているか
- 市区町村が交通安全施設を整備する箇所を決める際に、「交通事故の実績をおおむね参考にしている」と回答した市区町村は1割しかなく、「交通事故の実績をほとんど参考にしていない」と回答した市区町村が4割もありました。
- 市区町村では、住民からの交通安全対策に関する要望や、通学路の合同点検で把握した危険な箇所に向けて交通安全施設を整備することが基本となっています。交通事故の発生箇所や事故リスクが高い箇所を把握して交通安全施設を整備するのを基本としている市区町村はごくわずかでした。
- 交通安全施設を整備する箇所を決める際に、事故多発箇所を重視していない市区町村が半数以上で占め、潜在的高リスク箇所をほとんど参考にしていない市区町村も8割近くを占めました。
- 市区町村は、国土交通省(国道事務所)からETC2.0加工情報の提供を受けることによって、潜在的高リスク箇所を把握することができるようになります。しかし、この情報は、ゾーンでの対策を実施する場合にのみ提供され、個々の箇所への対策では提供されないと誤解している市区町村がありました。
どのような種類の交通安全施設を整備するかをどうやって決めているか
- 交通安全施設の種類を決める際に、「交通事故の内容をおおむね参考にしている」と回答した市区町村は3割程度で、「交通事故の内容をほとんど参考にしていない」と回答した市区町村も2割ありました。
- 交通事故の実績や事故内容を十分に把握しないまま、現場の道路・交通の環境を見た上で担当職員の経験則に基づいて整備する交通安全施設の種類を決めている市区町村が多数を占めました。
- 市区町村からは、「交通事故統計情報のオープンデータを使って事故内容を把握しようとしても、事故の要因や車両の進行方向等が掲載されていない」「国は、事故要因を踏まえた交通安全施設の整備方法を解説する資料を作成しているが、その内容は幹線道路向けになっていて生活道路では活用しにくい」といった意見が聞かれました。
- 都道府県警察から交通安全施設の種類に関する提案をほとんど受けていないとする市区町村が2割程度ありました。
交通安全施設を整備する場所を決める際に、交通事故の実績を参考にしていなかったり、そもそも交通事故の発生箇所すら把握していない市区町村があるのですね。ほかにも、どのような交通安全施設を整備するかを決める際に、発生した交通事故の内容をほとんど参考にしていない市区町村があるとは…。
こうした市区町村には、それぞれ事情があるのかもしれませんが、こうした現状を初めて知り、軽いカルチャーショックを受けましたね。
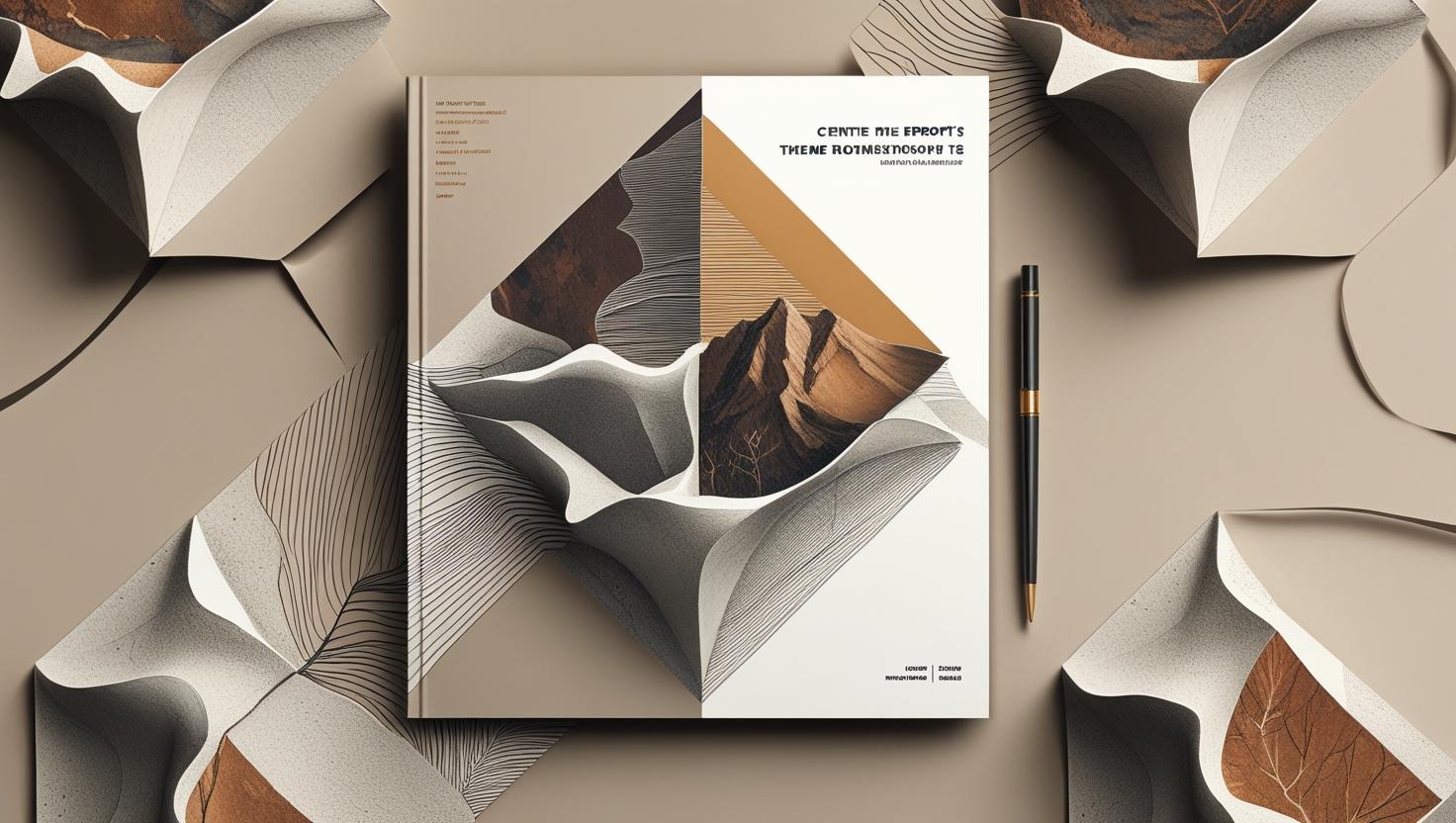


コメント